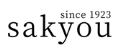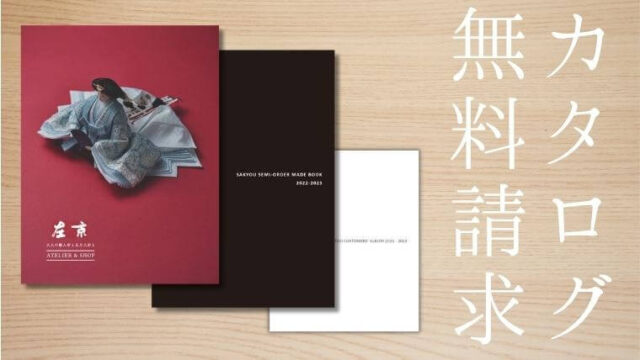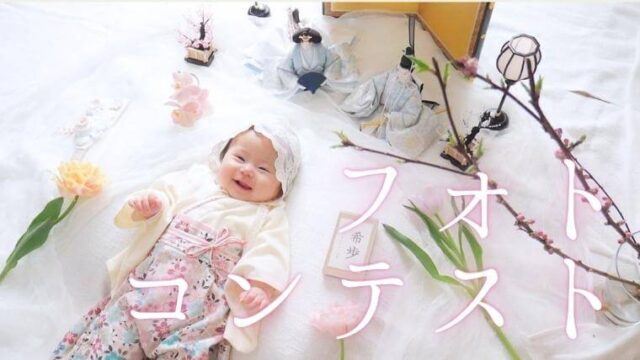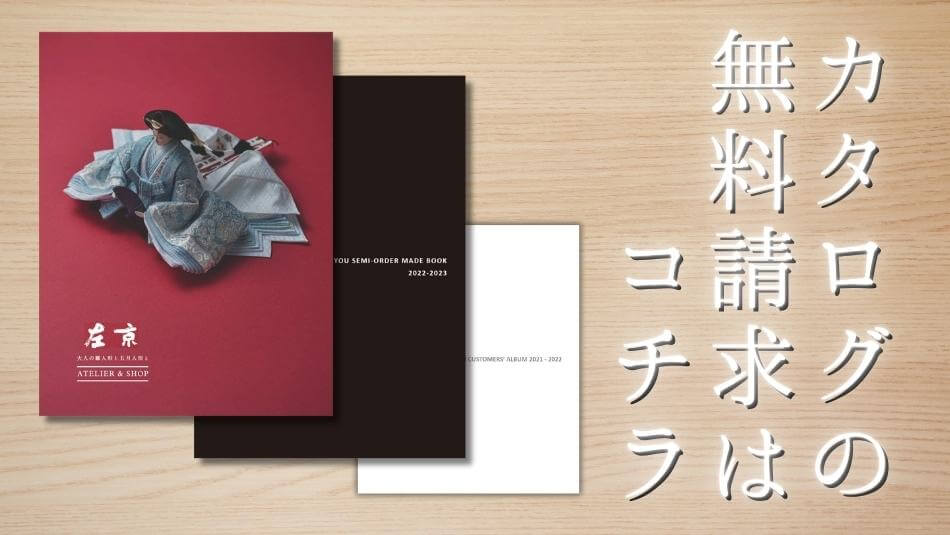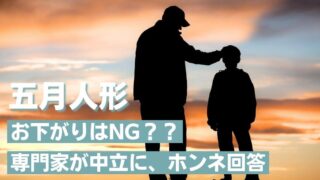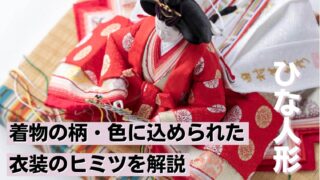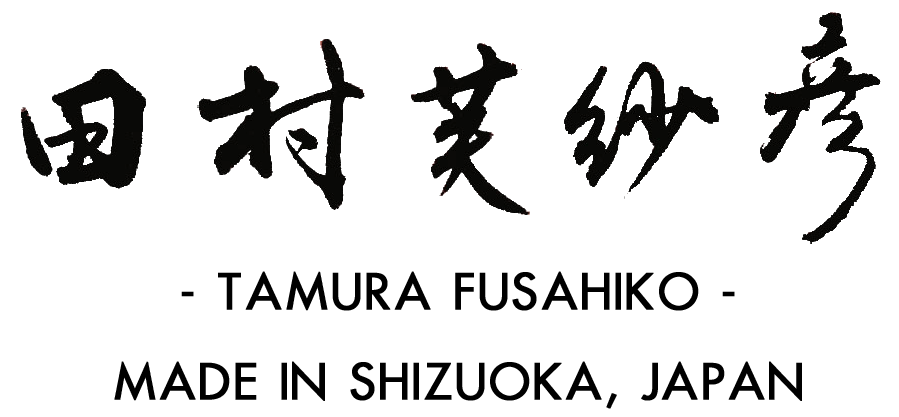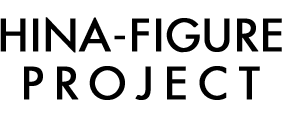「大切にしていた雛人形、処分しなきゃいけないけど丁寧にお別れしたい!」
「雛人形って、ゴミとして捨てたらなんか呪われたりするのかな?」
「雛人形っていつまで飾るんだろう?ずっと飾っておくのは変なのかな?」
雛人形は女の子の身代わり、お守りとしての役割を持つ人形。その役目をいつ終えるのか、また、役目を終えた雛人形はどうすればいいのか、など雛人形との「お別れ」に関する質問をよくいただきます。
そこで今回は、創業約100年『人形工房 左京』の4代目跡継ぎが雛人形の処分について、タイミングや方法を徹底的に解説します!
雛人形とのお別れに関するあらゆる疑問を解消できるので、ぜひご一読ください!
雛人形を処分するタイミングは「自立」した時!

雛人形は本人の「自立」のタイミングでお守りとしての役割を終えます。昔は自立といえば主には「結婚」でしたが、現代には様々な形での自立がありますね。
結婚はもちろん、進学や就職を機に実家を離れることも珍しくありません。そういうのも自立ですよね。一人前の大人になったという意味では「成人」を自立のタイミングとする考え方もあります。
「具体的にはいつ?」
と言われると絶対の正解はなくて、それぞれの考え方が一番大事です。「もう立派に自立した!」「人形に守ってもらわなくて大丈夫!」と思えるようになった時が、人形が本来の役割を終えた時。
その節目になるのが、成人、結婚や、実家を離れるなどのタイミングなのです。
雛人形の処分方法5つ!自分が納得する形であればOK

役目を終えた雛人形の処分方法ですが「こうしなければならない!」もしくは「こういう方法は絶対にNG」といった絶対の正解・間違いはありません。
一般に取られることの多い方法、迷われる方の多い方法を5つ紹介します。
- 神社やお寺で人形を供養
- 日本人形協会の供養代行サービス
- 自分でゴミとして処分
- 人にあげる、お子様へのお下がりに
- リサイクルショップやフリマ・オークションで販売
神社やお寺で人形を供養する
丁寧に人形とお別れする方法として、神社やお寺で供養する方法が挙げられます。お焚き上げや読経で丁寧に人形を供養し、別れを告げることで後悔やうしろめたさなく人形を処分できる、という方も多いのではないでしょうか?
人形供養後は不思議と、皆さんとてもすがすがしい表情をされます。
人形やぬいぐるみなどの供養を扱っている神社、お寺は探してみると意外と多いので気になったら探してみてください!
日本人形協会の供養代行サービス
「人形を供養したいけれど、近くでできる場所がない!」という場合、供養代行サービスを使うのもおすすめです。
一般社団法人日本人形協会では、自宅まで人形を引き取りに来てくれて、あなたの代わりに大切な雛人形の供養を行ってくれる、供養代行サービスを行っています。
「一番最後まで自分の手で丁寧に処分したい!」という部分にこだわりがなければ、手間の少なさと丁寧さのバランスがちょうどよく、おすすめできる方法です。
自分でゴミとして処分する場合は感謝の気持ちを込めて
ご自身の気持ちに抵抗がなければ、自分でゴミとして処分しても問題はありません。
一番罪悪感や後悔が残りにくい処分方法は「供養」ですが、どうしても手間や費用がかかってしまいます。
そのままゴミとして扱うことに心理的な抵抗がある場合、捨てる前に気持ちを込めて手を合わせる、お塩を振りかけて清める、など感謝の気持ちを表すことで心の整理をつけるのも有効です。
呪いや祟りといったものは迷信!
「ゴミとして捨てたりすると呪われてしまう、祟られてしまうのでは?」
と気にされる方もいらっしゃいますが、雛人形にそういった呪い・祟りはありません(そもそもが「お守り」の人形ですからね)。
呪いや祟りといったものの正体は、人形をうしろめたさの残る方法で処分したことによる雛人形、そして雛人形を贈ってくれた両親・親戚の方々に対しての後悔や罪悪感です。
要は方法そのものが悪いわけではなく、その方法をとった本人の気持ちの問題であり、悔いの残らない形であれば、極論どう処分しても構わないということです。
人にあげる、お子様へのお下がりにする場合は厄払いをしてから
「大切な人形だから大切な人に」
と、知人にあげたりお子様へお下がりにしたい方もいらっしゃいます。
これは本来の雛人形の役割を考えるとおすすめできる形ではありません。雛人形は本来一人一つ、子供の厄を受けてくれる身代わりなので、もらう側からしても「お下がり」は気になります。
どうしても譲りたい・譲り受けたい場合は、そういった雛人形の役割と文化を知った双方が、了承の上でやり取りを行うようにしましょう。
ですが、あなたの厄が残っている人形をそのまま人にあげてしまうのはやはり良いこととは言えません。万が一何かしらの厄にあった時、「人形をあげたせいかもしれない」なんて思いたくないですよね?そういった場合はまず神社やお寺などで厄払いをしてからにすることをおすすめします。

リサイクルショップやフリマ・オークションでの販売は?
リサイクルショップやフリマアプリで販売することについても基本的な考え方はお下がり同じで、本来の意味から考えるとおすすめはできません。
販売したい場合は販売前に厄払いをおすすめします。赤の他人が知らないところで自分の厄を被るかもしれない、なんてあまり考えたくもないですよね。
それに、元をたどればお子様の出生を祝って両親や親戚がくれた贈りものであることがほとんどのはず。大切な人からの贈りものを中古品として販売してお金に換えることはあまり良い行いとは言えませんね。
ちなみに中古での雛人形の売買はそれほど活発ではありません。思ったほどの価格がつかなかったり、そもそも売れないことも珍しくないので、コストパフォーマンスから考えてもおすすめできません。
役目を終えた雛人形を処分せずインテリアとして飾るのも◎

「愛着がある」「人形として好き」といった理由で雛人形を手放したくない場合は役目を終えた後もインテリアとして生涯大切にしても全く問題はありません。
雛人形は本人の自立のタイミングでお守りとしての役目を終えますが、役目を終えた雛人形は必ず処分しなければならない、そのまま置いておくと何か悪いことが起きる、といったことはないのです。
「愛着があって残したいけどインテリアとして飾るには大きすぎる」いう場合には、一番上のお殿様・お姫様だけを残すような形もよく取られます。
まとめ

雛人形が本来の「お守り」としての役目を終えるのは、本人が立派な一人の大人として自立するタイミング。
そして処分する際大切なのは方法そのものではなく、その方法を取るご自身の気持ちです。ぜひ、雛人形に感謝の気持ちを伝え、後悔しないお別れの方法(もしくはお別れしないで飾るという選択)を考えてみてください。
雛人形の処分方法でもその他迷われることでも専門家に聞いてみたいことがあったらお気軽にご連絡ください!